| 現に在(あ)る政治の世界はたしかにみにくく空(むな)しい。しかしそこはすくなくとも、あらゆるひとびとの生活にかかわってゆく場所である。現実社会の痛ましい、人間の事実に直接ふれることのできる場所である。そのことが太子をとらえてはなさなかったのである。 太子は義務感にしばられて摂政にたたれたのではない。自分の力を恃(たの)んで、ひとつやってみようとおもいたたれたのでもない。もちろん太子が摂政にたたなければならなかった事情はいろいろとあったが、その事情に応じて摂政にたたれたのは、そうせずにはおれないふかい願いにうごかされてのことであった。「一切衆生(しゅじょう)病(や)めるをもって、この故に我病む」という維摩経(ゆいまきょう)の言葉に心をとどめられ、また勝鬘経義疏(しょうまんぎょうぎしょ)のなかに「衆生はことごとく仏となるべきに、しかも衆生はことごとく仏となることなければ、すなわち如来の常住(じょうじゅう)なること明らかなり」と書きしるしておられるのも、太子が、世に病める人あるかぎり自ずからもまたその病をともに病み、迷っている人があるかぎり自分もまたどこまでもともに迷っていくというその姿に、仏道に生きる者の姿をみていられたことをものがたっている。しかもそれが、太子の生涯をつらぬく生活態度であった。太子が摂政の座にたたれたのは、じつにその第一歩であったのである。 太子にとって直接のみちびきとなったのは維摩居士(ゆいまこじ)の姿であった。太子が維摩居士をたたえて述べておられる有名な言葉、「国家の事業を煩(はん)となす。ただ大悲やむことなく、志は益物(やくもつ)に存す」とは、じつは摂政としての太子自身の心をみずからかたっているものといえる。(東本願寺発行「太子讀本」より) |
|
| 皇太子聖徳奉讃 聖徳皇のおあわれみに 護持養育たえずして 如来二種の回向に すすめいれしめおわします 久遠劫よりこの世まで あわれみましますしるしには 仏智不思議につけしめて 善悪浄穢もなかりけり |
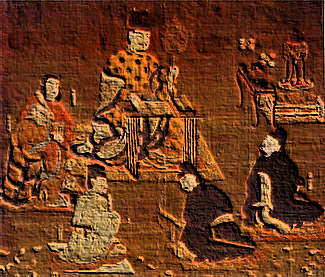 |
| <住職のコメント> 聖徳太子は、どのようにして民衆を護り育てたのか。それは、「善悪浄穢」という人々を上下に分断する、人間の思い込みから、人々を解放する事によってなされた。太子のエピソードの一つに、「行き倒れ」の死人に太子が出会った話がある。その時太子は、さらりと紫の衣をぬいで、死者に掛け、手厚く葬る事を指示し、終った後、また、その衣を身に着けたという。そのように具体的に上下の身分、穢れ意識を軽やかに超えて、水平な人の交わりを創ろうとした方であった。 |
|
―――以上 『顛倒』04年8月号 No.248より―――
前号へ 次号へ
目次に戻る
瑞興寺ホームページに戻る